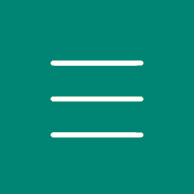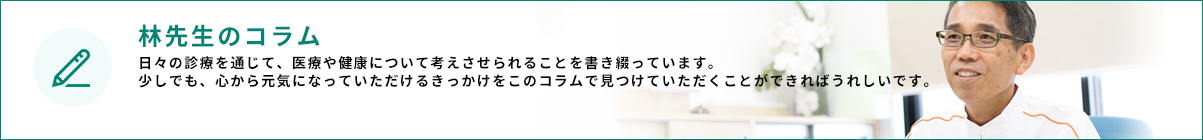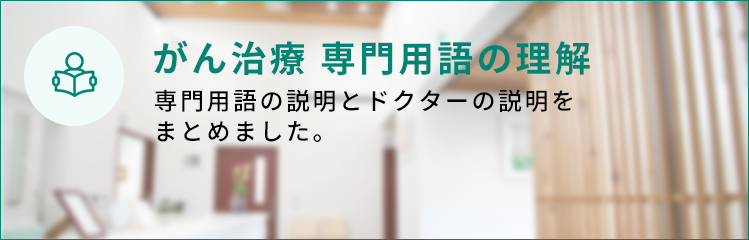がん治療 専門用語の理解のためにTerms
がん治療 専門用語の理解のためにTerms
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、診断や治療方法について、主治医以外の医師の意見を聞くことをいいます。
別の医師の意見を聞くことで、納得のいく治療を選択しようとするものです。
主治医の薦める治療法でいいのだろうか?それが最善の治療法なのだろうか?
基本的に、日本のどの病院でも、保険診療により同じ治療が受けらるという前提があります。
ですから、常識的には、その標準的な治療の妥当性を確認するのがセカンドオピニオンの実質的な効果ともいえます。
よほどのミスやゆがみによる判断がない限り、主治医の診断や治療法に同意されるケースがほとんどだろうと推測されます。
患者さん側にとっては、もっと良い治療法はないか。
主治医の先生は厳しいことを言っているけれども、ホントは、助かる方法があるのではないか・・・
などとして、セカンドオピニオンを求めることが少なくないと思います。
通常の「ガイドライン」にのっとって診断や治療法の選択が行れている限り、どの病院のアドバイスも、基本的に変わることはあまりありません。
基本的には、ドクターの「立ち位置」によるのです。
治療法は、正しく診断されて、正しく選択されると、「教科書的には」ひとつの正解にたどり着くことになります。
しかし、人それぞれ、年齢や、家族環境、社会的環境などのほか、考え方や希望も違います。ですから、現実には答えはひとつとはなりません。
だからこそ、治療法は、自分で選ぶということにつながります。
それぞれの人の生き方に、直接かかわる問題です。
生活者としての患者さんの世界にさらに一歩踏み込んで考えてみますと、医学的に正しい治療法が、必ずしも患者さんや家族を幸せにするとは限らないということがあります。
病状を正しく理解して、静かに人生を振り返ることをしてみて、そのうえで治療を考える、そんなこともあっていいのではないでしょうか。
インフォームドコンセント
治療の方法や意味、効果、危険性、その後の予想や治療にかかる費用などについて説明を受け、そのうえで治療の同意をすることを言います。
「説明と同意」という意味あいです。
インフォームドコンセントは、治療をすすめる上での単なる「手続き」ではありません。患者さん自身が、自分で医療を選びとっていくという意味あいがあります。
もちろん、医師と患者の間には知識の大きな差があります。それでも、正しく理解をして、自分で選びとるという姿勢がインフォームドコンセントの価値を決める肝心なところです。
病状の詳しい説明や、薬に期待される効果や予後の説明など、ていねいに説明されても、理解するには骨がおれるかもしれません。
理解が多少不十分でもついつい同意せざるを得ないムードになってしまうのも現実としてあるかもしれません。
説明する側の問題と、説明を受ける側の課題とがあるでしょう。
がんの診断で、厳しい説明があった時、いやだという心の叫び。なんで、こんな病気に、なんで私が、という思いは、誰にでも強くおこるでしょう。
手術、化学療法、放射線療法・・・という標準的な治療の流れ。その「標準の流れ」に乗る前に、これまでの自分の人生とこれからの人生をじっくり見渡すことが大切です。
じっくり考える時間を持つことで、「本当の同意」をすることができるのかもしれません。治療の意味を考え、生き方を考えます。
医療技術面だけから考えたのでは、自分の納得のいく方向を見つけるのはなかなか難しいかもしれません。
標準治療 ガイドライン
各種のがんをステージ分類して、ステージ別の治療方法を整理しています。
治療方法には、手術、化学療法、放射線を含めていろんな組み合わせがあります。
治療データを大規模に集め、統計的な整理を行い、広く認められている治療方法が「標準治療」として、がん治療の中心的な病院(基幹病院)で行われます。
大まかにいえば、ステージⅠの初期の段階なら手術。ステージⅢやステージⅣなら、生存率を上げるためにできる治療として、これとこれ、というように。
データの裏付けのあるもの、効果の確認されたものが標準治療として採用されます。
その標準治療を実際に運用するうえで、基本的な決めごとを、判断基準や、手順などを専門家が整理したものをガイドラインと言います。
基本的に治療は、この標準治療とガイドラインを目安にすすめられることになります。
さて、標準治療がそのまま、患者さん個人にとって、必ずベターな選択になるかと言えば、それはわからない、と言わざるを得ません。
同じがんで、同じ進行度でも、お一人おひとりの生活背景が違います。人生のとらえ方も違います。
医学的判断は一つの材料になりますが、最終的には、ご本人の考え方しだいです。
とことんがんの治療を行い、体力がある限りどこまでも手術や抗がん剤で立ち向かうというのもあります。「がん治療をすることが生きることだ」という選択です。最近の有名人の例でいいますと、食道がんとなった歌舞伎役者の中村勘三郎さんのように手術を抗がん剤治療でとことん闘ったというもの一つの例でしょう。
また、治療はそこそこに、残された時間を生涯をかけてやりとげたい仕事やイベントに精力を傾けるという考えもあります。
病気のことは忘れて、徹底的に命を燃やすというのもあるでしょう。有名人の例ですと、緒方拳さんは、肝臓がんを持ちながらも最期の最期まで役者として生きられました。
喉頭がんと診断された歌手の忌野清志郎さんは、最期まで歌をうたいたいから、と手術されませんでした。たとえ半年寿命が縮まったとしてもいいから、ということで、自分の命を生きられました。
もちろん、そのためには、それなりの考えの整理とそれをするだけの家族を含めたサポート態勢が重要になってきます。
いずれにしても、人それぞれの「選択」があるということです。標準治療というのは、その中のひとつの例ということでしょうか。
エビデンスとEBM
エビデンスは、科学的根拠のことです。
たとえば、薬の開発などでは、動物実験、一般健康人(フェーズ1)、少数例の患者さん(フェーズ2)、さらに臨床試験やダブルブラインドの試験などの手順をへておこなわれます。
こうした研究対象群でのデータを厳格に統計処理をして、その薬が有益であるとの評価をされたものを科学的な根拠があるとされます。
その科学的根拠には、質の高いものから低いものまでいくつかのレベルがあり、ランダム化比較試験が最もエビデンスレベルが高いとされています。
エビデンスは、薬以外にも治療方法、検査方法など、医療の内容全般について求められる科学的判断の根拠ということになります。
EBMは、その科学的根拠に基づく医療という意味あいになります。
(Evidence-Based Medicine)
エビデンスを集める最初の段階では、基本的に、個体差はほとんどないという「条件」の整理をされています。
臨床試験の段階で、いよいよ個々の人間にあてはめられます。
さらに、実際に、医療の現場になりますと、ひとそれぞれ食生活や、睡眠時間や、生活環境など、違う条件が様々にあります。
研究成果は研究成果として、現実に対応させるには、その個別性をどのように「見ていくか」というのが、医療の現場で、要求されるものだと考えています。
EBMは、科学的根拠に基づく医療として、「医療者の専門性と患者さんの希望とを総合して医療上の判断を行う考え方」と定義されています。
エビデンスをそのまま、患者さんの「表面的な希望」に結びつけるだけでは、本来の希望につなげることはできないのではないかと思っています。
ステージ(病期のこと)
がんがどのくらいの大きさになっているか、どの程度組織の中に広がっているか、周辺のリンパ節にいくら転移しているか、遠隔臓器への転移はあるかなどの要素をもとに、がんの進行度と広がりの程度を表わすのが ステージ(病期)分類です。
ステージは、I期(IA、IB)、II期、III期(IIIA、IIIB)、IV期に、大きく分類されます。
がんの種類別にそれぞれにステージ分類があり、それにあわせた標準的な治療法が用意されています。ガイドラインといいます。治療の有効性は5年生存率を一つの目安にしてデータが集積されています。(詳しくは、国立がんセンターのサイトへ)
ステージは、治療前の検査によって決まりますが、手術の時に転移などが見つかれば、変更されることもあります。
遠隔転移をしている場合には、手術でもとの腫瘍をとるだけでは、根治はむずかしくなります。ですから、ステージによっては、症状を抑えるだけの手術・・・緩和的手術にとどまることもあります。
今後の希望を整理するうえで、ステージとそれに対する治療の内容については、正確に理解することが、患者さんや患者家族にとっては、とても大切なことと思います。
ステージの判定は、医療者にとっては、治療方法の選択のための判断材料になります。患者さんにとっては、どのような治療が提供されるか、という切実な課題に直結します。
医療者にとって、どれだけ生存期間の伸ばせるか、これが一つの大きな判断基準となります。患者さんにとっては、長さも気になるところですが、「治る方法」があるのかないのか、ということではないでしょうか。
注意をしないと、ここにズレがあると、治療結果に不満をもつことにつながりかねません。奇跡的回復を願う気持ちとは別に、冷静に、ステージの常識的理解をすることは大切だと思います。
QOL(生活の質)を保つ
QOL・・・Quality of Life(クオリティオブライフ)の略で生活の質のことを言います。患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。
病気の症状や治療の副作用などによって、治療前と同じようには生活できなくなることがあります。
このような変化の中で、「自分らしい生活の質の維持」を目指すという考え方です。
治療法を選ぶときには、治療効果だけでなくQOLを保てるかどうかを考慮していくことも大切とされています。
QOLを保つことへの配慮はとても大事だと思っています。肉体的な面だけでなく、精神面も重要な要素です。
今までと同じようなライフスタイルを営めるかどうか。
QOLは、一人ひとり違います。その人自身の価値基準によります。ですから、第3者には、なかなか分かりずらい面があります。自分の願いを冷静に整理することも大切でしょう。
がんを何が何でも治療でやっつけようとするあまり、QOLがズタズタになるのは、どうなんでしょう。
病状が厳しい状態にある場合、療養生活がどのような状況にあるとしても、ある意味精神の安定性が保たれていれば、QOLは保たれていると見ることもできます。
再発や腫瘍マーカーの上昇、それに検査で画像サイズが大きくなっているとの報告で、気分が落ち込むこともあるでしょうが、病気に振り回されないという知恵がQOLを保つ秘訣の一つかもしれません。
では、それをどのようにして手に入れるか。
「生きてるだけで儲けもの」という言葉が、そのヒントのひとつかと考えています。
治療法の選択
がん治療には、手術治療、薬物療法、放射線治療の3つがあります。
がんの種類や進行度によって、治療法の選択肢が複数あることもあります。
担当医は、病気の状態に合わせて、最適と考えられる治療法やほかの治療法を選択肢として提示し、説明します。
どの治療法を選ぶかを決めるのはご本人です。わからないことがあれば理解できるまで担当医に質問したり、自分で調べることが大切です。
セカンドオピニオン を参考にすることもできます。
食道がんの治療選択で。
主治医は手術ができるというので、手術を勧められた。放射線や化学療法は効果の期待が薄いとも。
どのような治療を選択するにしても、その治療のあとどのような生活になっていくのか十分に理解することが大切です。年齢やその後の生活を考慮すると「からだに負担の大きい治療はやめておく」というのも一つの選択枝となります。
いずれにしても、自分のことですので、遠慮しないで、ドクターにはしっかり聞いていくことが必要です。その中で、自分の価値基準に照らし合わせて、どのような選択がいいのか見えてくるはずです。
どんなことを聞いても恥ずかしいと思わないことです。
ご自分の命のことです。
どのような生き方をしていくかは、ご自分でしか決められません。
当院では、時には、患者さんに、手術担当医などとの良好なコミュニケーションの取り方のアドバイスもさせていただいてます。
五年生存率
治療で、どのくらい生命を救えるかを示す指標です。
治療5年後に生存している人の割合が、がんに関係ない人の5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表されます。
パーセンテージが高いほど、治療で生命を救えるがんとされています。ですから、がんの治療成績を示す指標として使われます。
この生存率は、ステージや治療法により異なる治療成績の価値を判断するものさしのひとつとして使われます。
5年生存率が40%というのは、5年後、10人のうち4人が生きているということを示しています。
生存率40%と説明されると、誰しも、5年生きられる方に魅力を感じ、自分もそうなると考えます。自分が5年以下の6人の側に入るとは思いません。
5年後に自分はいない。そんな想像、誰もしたくありません。4年8か月後、つまり5年でいなくなるということもデータの中には入っているのですが。
さて、いずれも命の長さに焦点を当てています。
医療者の善意、思いは「長さ」にあります。
これが必ず患者さんの「益」になるかどうかは、わかりません。
がん治療で、ベッドの上でようやく生きているのも「生きているデータ」に含まれます。データからは見えないものがあります。
とことん、がん治療に立ち向かうのもいいでしょう。抗がん剤でがんばって生きるというのもひとつ。趣味の音楽のステージに立ちたいと、病気をおさえながら懸命に努力を重ねる人もいます。また、がんの治療はそこそこに、とことん仕事に打ち込んでいく人もおられます。
家族との旅行や、食道楽に突き進む人もいるでしょう。
生まれてくる孫の顔を見るのを楽しみに、少しでも生きながらえようと踏ん張る人もおられます。
それぞれの思いがそこにあります。
すべては、考え方一つで決まるのではないでしょうか。そのために出来る医療の支えは、いろいろあります。
分子標的治療
抗がん剤は、細胞傷害の作用で、がん細胞を攻撃します。
そのため、同時に正常細胞まで痛めつけることになります。
それに対し、分子標的治療薬は、がん細胞の増殖や浸潤、転移に関わる分子を標的として、その分子を阻害し、がんの増殖を抑えたり進展を阻害しようとします。
がん細胞に特異的に効果を示すことが期待できるとされ、近年、その新薬の認可や使用は年々増える傾向にあります。
たとえば、ハーセプチン(転移性乳がん)、グリベック(慢性骨髄性白血病や消化管間質腫瘍)リツキサン(悪性リンパ腫)、イレッサ(肺がん)、タルセバ(肺がん、アバスチン(大腸がん)などです。
一般に、旧来の抗がん剤に比べて、毒性は低いとされ、延命効果を得られるとされています。
それでも、徐々に効かなくなるという「薬剤耐性」の問題もあり、ずっと使い続けるのが困難になってくる場合もないとは言えません。
薬にはそういう要素があります。
薬による治療もやはり「限界がある」ということを知っておくことが大切です。
腫瘍マーカー
がん細胞の中には、特徴的な物質を作りだすものがあります。
そのような物質のうち、、血液中で測定されるものが腫瘍マーカーとして利用されます。
腫瘍マーカーには多くの種類があります。
乳がんでは、CA-125、CA15-3、CEA、大腸がんではCEA、NCC-ST-439、STNなどの腫瘍マーカーがあります。他にもあります。
腫瘍マーカーは、進行したがんの動態を把握するのに使われます。
腫瘍マーカーが、上昇していくと悪化していると判断したりします。
一つの参考にはなりますが、マーカーの動きが正確にがんの動きを反映しているとは限らないとされています。
がんが進行しても、腫瘍マーカーが上昇しない人もいます。 また、逆に、末期には、マーカーの数値が下がったりすることもあります。
むくみとたんぱくの低下
がんの病態が進みますと、血液中のたんぱく(アルブミン)が減少します。体の中で、たんぱくの「異化」が亢進されるからです。
身体のたんぱくが分解されて、血液中へのアルブミンの補充が進まず、結果的に、アルブミンが少なくなっていきます。
また、出血もしていないのに、ヘモグロビン(たんぱく質)が減ることもあります。
手足のむくみ症状は、リンパ節転移や、術後の血液循環の不全などに生じる場合の他、進行したがんの場合は、血液中のたんぱく(アルブミン)の減少などが考えられます。アルブミンは、血液の中の水分の量を調節する働きがあります。血液循環の悪いところでは、その浸透圧が低下するので、血管から水分が漏れ、むくみとなって現れます。
また、たんぱく質が足りないと、血管・免疫細胞・筋肉などの組織がスムーズに作られなくなり、体にさまざまなトラブルが起こります。
ですから、血液中のたんぱくを減らさないようにすることは、寿命の延長にとっては大事なことになります。
最近は、玄米菜食に熱心に取り組む人がいたりしますが、ほどほどにしておいた方がよいのでは、と思うことがあります。
栄養バランスという観点からすると、やはり消化の良い良質なたんぱく質を摂取することが大事です。
むくみの原因が低アルブミン状態ではない場合には、症状をとるのにいくつかの方法があります。
「リンパドレナージ」やソフトなタッチでリンパの流れを良くする「整膚」のほか、リンパや血流を改善するために筋肉を強くしてドレナージ力を上げるという「筋膜トレーニング」という方法などがあります。
■生化学の観点からの補足
たんぱく質のもとになるアミノ酸が結合する時、その反応過程で、水分子が増えます。このたんぱく質の「同化」作用により、細胞レベルでは、「みずみずしい」状態が出現します。
細胞分裂の盛んな赤ちゃんや子供の肌が、みずみずしい理由です。
反対にたんぱくの「異化」作用には、水が使われて分解していきます。
高齢になり、代謝が鈍って、異化作用が増えると、細胞の水分がへり、しわが増えることにつながります。
これらは、からだの細胞の中で起こる生理現象です。
予後
病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。
「予後がよい」といえば、「これから病気がよくなる可能性が高い」、「予後が悪い」といえば、「これから病気が悪くなる可能性が高い」ということになります。
この場合、 この先どれくらいの期間の長さを生きられるかという「生命予後」のことが含まれていることがあります。
「予後」という専門用語では、一般の人にはなかなか分かりづらいことが残ってしまいます。
予後が悪いという場合、これから先、「どういう経過をたどって、どれくらい先まで生きられますか」という、命にかかわる問題であるという認識が必要かもしれません。
予後がかなり悪いと判断される場合には、治療を受けないという人が出てくる場合もあるでしょう。逆に、とことん病気と闘うことで人生を燃焼させようという人もいるでしょう。最近は、「それなら好きなことをしたい」という人が、昔に比べて思った以上におられるのかもしれません。
病気をどのようにとらえるか。
このことが治療の選択や、予後の判断に対する対処の方法を決定ずけていくものになるのでしょう。
がんと老化と生活習慣
「がんは老化という現象のひとつである」という見方があります。
小児がんがあったり、若い方の乳がんや胃がんがあったりもするので、すべてのがんが老化現象とは必ずしも断定はできませんが、50歳代ぐらいのがんは、老化が早期に現れたと考えられなくもありません。
80歳代、90歳代の人のがんは老化にともなう細胞の変異ととらえるのに異論は少ないでしょう。
それでも、がんという病名がつけば、それは、老化とするよりも、「疾患」ととらえて、治療の対象と考えられるものとなります。
もし、がんが、老化の一面の現れだとの認識が強くあるとすれば、極端な場合は、「そのまま、自然の成り行きに任せる」という考えもあながち的外れとは言えないと考えられます。
がんは、食べ過ぎや運動不足、それに喫煙などの生活習慣の乱れが関係していると言われています。
それでも、食生活に注意したり、適度な運動したり、タバコを吸わないひとでもがんになる人がいます。
睡眠不足や、仕事のしすぎなど過度のストレス環境が誘因になっているともいわれます。
これをすれば、必ずがんは防げるというものはなかなかないのが現状ではないでしょうか。
ある面、防ぎようがないとも言えます。
もし、そう考えるなら、ちょっと立ち止まって、出来るだけ「快適に日々暮らす」という「柔らかな視点」も役に立つのではないでしょうか。
がんになる前も、なってからも。
当院のがん治療Treatment
-

温熱治療
マイクロ波照射によるがん活性消滅療法(CEAT)
がん細胞は自ら増殖します。それに加え他の「正常な細胞をがん化するためのエネルギー」を持っています。
-

血液オゾン療法

体外で血液をオゾンガスと反応させた後に点滴で体内に戻します。
-

高濃度ビタミンC点滴療法

超高濃度のビタミンCは、強力な酸化作用を発揮し、がん細胞に対して抗がん剤のような毒性を示します。
-

プラズマパルサー(還元電子治療)

活性酸素を作らずにATPを3倍にします。 マイナス電子は様々なストレスによって破壊されてしまいます。
-

分子整合栄養学療法

分子栄養学観点から血液データを分析し、治療に役立てます。 血液中の酵素やミネラルなど様々な補因子を考慮します。
-

高純度水素点滴/注射療法

水素は皆さんの日常の生活の中でおこる、活性酸素による遺伝子の損傷から防いでくれます。
-

再生医療

乳歯歯髄幹細胞を培養する際、作り出される培養上清液です。